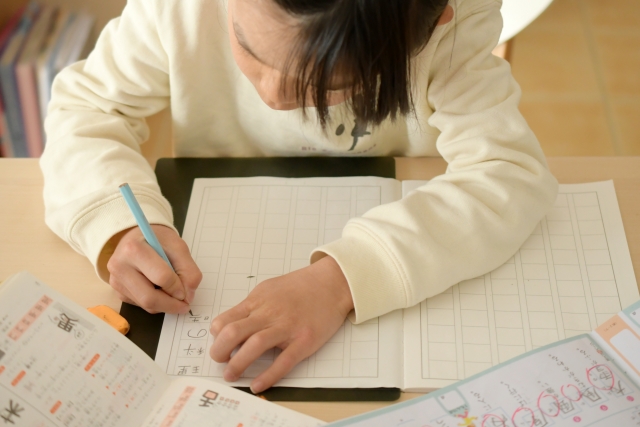こんにちは!個別指導WAMです(^^)/
本日は【英語の目的語とは?例文付きで詳しく解説!】について、お話したいと思います。
英文を構成する重要な要素は、「主語」「動詞」「目的語」「補語」になります。
なかでも、「目的語」がイマイチ分からない、という方が多いのではないでしょうか。
この記事では、「目的語」について詳しく解説します。ぜひ英語学習の参考にしてみてください!
Contents
SVOCについて
文の要素 (SVOC)
まず、目的語について解説する前に《英文を構成する要素》《5つの基本文型》《自動詞と他動詞》について簡単に説明していきましょう!
英文は基本、主語(S)・動詞(V)・目的語(O)・補語(C)の要素で構成されています。
・主語(S)は、日本語でいう「~は」「~が」にあたる語です。
・動詞(V)は、「~をする」「~である」といった主語の動作や状態を表す語です。
・目的語(O)は、「~を」「~に」に当たる部分であり、動詞の目的を表す語です。
・補語(C)は、主語または目的語の意味を補う語です。
5つの基本文型
「5つの基本文型」とは、主語(S)・動詞(V)・目的語(O)・補語(C)で構成された文の構造を5つのパターンに分類した英文の型のことです。
第1文型【S+V】
第2文型【S+V+C】
第3文型【S+V+O】
第4文型【S+V+O+O】
第5文型【S+V+O+C】
自動詞と他動詞
動詞には目的語をとる動詞「他動詞」、目的語をとらない動詞「自動詞」の2つに分けることができます。5つの基本文型では第1文型、第2文型が「自動詞」、第3文型~第5文型が「他動詞」になります。
自動詞の例文
She cried.(彼女は泣いた。)
→「cried(泣いた)」が自動詞になります。
他動詞の例文
He likes soccer.(彼はサッカーが好きです。)
→「 likes(好き)」が他動詞になります。
目的語とは
目的語とは、日本語でいう「~を」「~に」に当たる部分であり、動詞の目的を表す語になります。
目的語は常に他動詞の後ろに置かれています。実際に目的語が含まれる文型で確認してみましょう。
①第3文型【S+V+O】
第3文型の基本的な意味は「SはOをVする」となります。
例:I bought an apple.(私はリンゴを買いました。)
→主語はI(私)、動詞はbought(買った)、目的語はan apple(リンゴ)になります。
②第4文型【S+V+O1+O2】
第4文型の基本的な意味は「SはO1にO2をVする」となります。
O1には〈人〉、O2は〈物、こと〉が入ることが多いです。
例:He taught me study.(彼は私に勉強を教えました。)
→主語はHe(彼)、動詞はtaught(教えた)、目的語1はme(私に)、目的語2はstudy(勉強)になります。
③第5文型【S+V+O+C】
第5文型の基本的な意味は「SはOがCだと(するのを)Vする」となります。
例:I named the cat Tama.(私はその猫をタマと名付けました。)
→主語はI(私)、動詞はnamed(名付けた)、目的語はthe cat(その猫)、補語はTama(タマ)になります。
目的語になれる要素
目的語になる要素は、基本は「名詞・代名詞」ですが、「名詞的用法の不定詞」「動名詞」「名詞節・名詞句」などの名詞的な形を持つものも目的語になります。
名詞・代名詞
名詞とは人や生き物、物の名称を表す品詞、代名詞は名詞の代わりに使われる品詞になります。
目的語では主に名詞と代名詞が使われます。
・I ate a cake.(私はケーキを食べた。)
→名詞の「a cake」が動詞の「ate」の目的語になります。
・Tom likes her.(トムは彼女が好きだ。)
→代名詞の「her」が動詞の「likes」の目的語になります。
to不定詞の名詞的用法
to不定詞は「to+動詞の原形」という形で、名詞的(~すること)・形容詞的(~するための)・副詞的(~するために)の3つの用法あります。to不定詞の名詞的用法(~すること)は、名詞のような働きをするので動詞の目的語になります。
・I decided to go to the hospital.(私は病院へ行くことを決めた。)
→名詞的用法のto不定詞「to go」が動詞の「decided」の目的語になります。
動名詞
動名詞とは「動詞+ing」で「~すること」という意味になります。
動名詞は名詞として扱われるため、動詞の目的語になります。
・I like making cakes.(私はケーキを作ることが好きです。)
→動名詞の「making」が動詞の「like」の目的語になります。
名詞節
2語以上のまとまりで「主語+動詞」を含み、名詞の役割を果たすものを名詞節、動名詞やto不定詞の名詞的用法などの「主語+動詞」を含まないものを名詞句といいます。
名詞節には「that節」「間接疑問文」「what節」などがあります。
・He told me that he wouldn’t go to school. (彼は私に学校には行かないといった。)
→that節の「that he wouldn’t go to school」が「told」の目的語になります。
・I don’t understand what my son wants to do.(私は息子のしたいことが理解できない。)
→what節の「what my son wants to do」が「understand」の目的語になります。
・I don’t know why she is absent.(私はなぜ彼女が欠席しているのか分かりません。)
→間接疑問文の「why she is absent」が「know」の目的語になります。
目的語と補語の見分け方
第2文型「S+V+C」と第3文型「S+V+O」、第4文型「S+V+O1+O2」と第5文型「S+V+O+C」のように、目的語と補語は似たような位置にいるため混乱しますよね。そこで目的語と補語の見分け方について解説していきましょう!
・第2文型「S+V+C」と第3文型「S+V+O」
第2文型の基本的な意味は、「SはCである」となります。そのため、第2文型はS=Cの関係が成り立つことが特徴です。
例:I am a doctor.(私は医者です。)
→S(主語)=I、動詞(V)=am、C(補語)=a doctor
第3文型の基本的な意味は、「SはOをVする」となります。第3文型では「S=O」の関係にならない所がポイントです。
例:I ate breakfast.(私は朝ご飯を食べた。)
→S(主語)=I、動詞(V)=ate、O(目的語)=breakfast
つまり、目的語と補語の見分け方として、主語に注目して=の関係が成り立つ場合は補語、成り立たない場合は目的語と判断しましょう!
・第4文型「S+V+O1+O2」と第5文型「S+V+O+C」
第4文型の基本的な意味は、「SはO1にO2をVする」となります。O1には〈人〉、O2は〈物、こと〉が入ることが多いため、「O1=O2」の関係にならない所がポイントです。
例:She gave me a book.(彼女は私に本をくれた。)
→S(主語)=She、動詞(V)=gave、O1(目的語)=me、O2(目的語)=a book
第5文型の基本的な意味は、「SはOがCだと(するのを)Vする」となります。第5文型はO=Cの関係が成り立つことが特徴です。
例:He made me happy.(彼は私を幸せにしてくれた。)
→S(主語)=He、動詞(V)=made、O(目的語)=me、C(補語)=happy
つまり、目的語と補語の見分け方として、動詞の後の目的語が=の関係に成り立つ場合は補語、成り立たない場合は目的語と判断しましょう!
まとめ
【英語の目的語とは?例文付きで詳しく解説!】についてお話ししてきましたが、いかがでしたか?
目的語も含め、主語、動詞、補語は英文法の基礎となる重要なポイントです。しっかりと理解しておく必要があります。
英語の学習に不安を感じる方、もっと英語を深く学びたいという方は、ぜひ一度個別指導WAMへご相談下さい。
個別指導塾WAMでは、学力、学習状況、性格などから、その生徒にあった指導を行っているため、自分に合った英語学習ができます。